ビニールハウス解体はDIYと業者どっち?費用や手順を解説
「ビニールハウスの解体って、結局いくらかかるのか…」
「自分でやるか業者に頼むか迷っている」
そんな悩みありませんか。
できるだけ費用をおさえたいけど自分で解体できるか不安になりますよね。
この記事では、
- ビニールハウス解体の費用相場やDIYとの比較
- ビニールハウス解体業者に依頼したときの費用
- DIYで解体する際の手順や注意点
を解説しています。
また、記事の後半では補助金が利用できるかも解説しています。
ビニールハウス解体の失敗や後悔を防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。
ビニールハウス解体はDIY?業者依頼?判断基準を解説

ビニールハウスの解体は「DIYで行う」か「業者に依頼する」かを決める必要があります。
以下ではそれぞれの特徴を表と箇条書きで比較し、どんな人にどちらが向いているかをわかりやすくまとめました。
◆ DIYと業者依頼の比較表
| 項目 | DIY(自力解体) | 業者依頼 |
| 費用 | 安く抑えやすい(工具代・処分代別途) | 一般的に高め(相場:1坪あたり5,000~12,000円、1㎡あたり約1,500~3,600円の目安) |
| 必要な準備 | 工具・作業知識・廃材処理 | 見積もり依頼・契約 |
| 安全性 | ケガ・落下などリスクあり | プロによる安全対策あり |
| 作業時間 | 数日~1週間かかる場合も | 半日~数日程度 |
| こんな人におすすめ | 小規模なハウスを持つ方、時間に余裕がある方 | 大型鉄骨ハウスや古い構造の方、安全重視の方 |
◆ DIYを検討する際の注意点
- 支柱やパイプの撤去作業は意外に重労働
- 廃材の処分費や運搬費が後から発生する可能性がある
- 倒壊・事故のリスクを甘く見ないように注意
- 周囲に迷惑がかかるとトラブル(倉庫破損・近隣苦情)に発展する場合も
◆ 業者に頼むべきケース
- 高所作業が必要な大型の鉄骨ハウ
- 基礎コンクリートが埋まっている場合
- 安全性やスケジュール重視の方
- 廃材のリサイクル処理や回収を丸ごと任せたい方
見積もりは無料の業者が多いため、まず相談してみると安心です。また費用だけでなく、安全性や後処理まで含めて比較するのがポイントになります。
ビニールハウス解体を業者に頼む費用の相場は?

ビニールハウスを業者に依頼する場合の費用相場や注意点を解説します。
予想外の出費を防ぐには、解体費だけでなく、関連するコストや過去のトラブル事例にも目を向ける姿勢が欠かせません。
解体費用の目安
ビニールハウスの解体にかかる費用は、構造や規模によって異なります。
一般的な相場は以下のとおりです。
構造費用の目安(1坪あたり・1㎡あたり)
| 軽量なパイプハウス | 約1坪あたり5,000~8,000円(1㎡あたり約1,500~2,400円) |
| 丈夫な鉄骨ハウス | 約1坪あたり8,000~12,000円(1㎡あたり約2,400~3,600円) |
上記金額には撤去作業や廃材処分費用が含まれている場合もあります。見積り時にしっかり確認しましょう。また、解体の手順や地域によっても単価は変動するため、複数社からの比較が重要です。
「予算を抑えたい」と思う方も多いですが、安全対策や処理の手間を考えると、安さだけで選ぶのは危険です。適正な価格かどうか、対応が信頼できるかをしっかり見極めるのが大切です。
解体以外の費用が掛かる場合もある
ビニールハウスの解体費用は「作業代」だけではありません。
見落とされがちな追加費用として、以下のような項目があります。
見落とされがちな追加費用
- 廃材の運搬・処分費(特に鉄骨・鉄パイプが大量の場合)
- 基礎コンクリートの撤去費用
- 倉庫など付属施設の処分費
- 解体後の土地整備や整地費用
例えば、「ただのハウス解体」と思っていても、埋設基礎や水道・電気設備の撤去が必要になる場合があります。その場合、費用が数万円〜十数万円単位で増える場合も。
また、「予算を決めていたのに見積より高くなった」という声も少なくありません。費用に関する不明点は、見積もり時に細かく確認し、電話やメールでしっかり確認を取る必要があります。
解体工事におけるよくあるトラブルと回避策
ビニールハウスの解体では、予期せぬトラブルが発生する場合があります。
特に多いのが次のようなケースです。
トラブル発生の可能性があるケース
- 見積もり内容と実際の請求額が違う
- 廃材を不法投棄された
- 隣地を傷つけてしまった(フェンスや作物など)
- 騒音や粉じんで近隣トラブルになった
など
ビニールハウスの解体には、構造や周囲環境に応じた対策が必要です。トラブルを避けるためにも、現地調査を行い、書面で正式な見積もりを提示する業者を選びましょう。
また、産業廃棄物処理の許可業者かどうか、処理ルートが明確かも確認しておくと安心です。トラブルを未然に防ぐためには、「価格の安さ」より「信頼できる対応」が何より大切です。
ビニールハウスを自力で解体する方法は?

DIYでのビニールハウス解体を検討している方向けに、基本の作業手順や必要な道具、注意点をわかりやすく解説します。安全に配慮しながらスムーズに進めるためのポイントを押さえておきましょう。
解体の基本手順(ビニール剥がし→支柱解体→パイプ抜き)
作業をスムーズかつ安全に行うには、ビニールハウスを決まった手順で丁寧に撤去する必要があります。
基本は以下の3ステップに分けられます。
- ビニールを剥がす
→ 風で飛ばないよう、複数人でゆっくり剥がしながら回収・処理。再利用しないなら処分方法も要確認。 - 支柱や連結部品を取り外す
→ ボルトや金具を工具で外しながら慎重に作業。構造が不安定にならない順番が重要です。 - 地面に刺さっているパイプを抜く
→ 地中に埋まった鉄パイプは、テコの原理や専用器具で引き抜くと安全。
ビニールハウスの解体は、上から順に解体していくのが基本です。また途中で倒壊の恐れがあるため、支柱を抜くタイミングには注意が必要です。
DIYに必要な工具・道具一覧
ビニールハウスを自力で解体するには、最低限の工具と保護具が必要です。
主な使用アイテム
- モンキーレンチ・スパナ(ボルトやナットの取り外し)
- カッター・はさみ(ビニール切断用)
- バールまたは鉄パイプ抜き工具(支柱の引き抜き)
- 軍手・安全靴・ヘルメット(安全対策)
- ブルーシート(撤去物の一時保管や作業場所保護)
- 脚立または足場(高所作業対応)
解体作業は思った以上に力や体力が必要です。「軽い作業だろう」と考えて準備を怠ると、思わぬケガや事故に繋がるので注意が必要です。
さらに、ハウスの規模や構造によっては、電動工具や大型道具が必要になる場合もあります。事前に解体するハウスの状態をチェックしておきましょう。
自力で解体するときの注意点
自力での解体作業には、コストを抑えられる一方で、リスクや手間もつきものです。
以下は特に注意したい点です。
DIYで解体するときに特に注意したい点
- 強風時や雨の日の作業は厳禁(ビニールがあおられ危険)
- 支柱の撤去順を間違えると倒壊のリスクあり
- 解体後の廃材処理(鉄・ビニール)の分別と運搬方法を事前に決めておく
- 農業用施設でも産業廃棄物扱いになる可能性があり、違法処分は罰則対象
「近所の人がやっていたから自分にもできる」と思うかもしれませんが、実際にはビニールハウスの規模や構造によって作業の難しさは大きく変わります。少しでも安全面に不安を感じた場合は、無理をせず一部だけでも専門業者に依頼するのが安心です。
ビニールハウス解体には補助金は使える?

ビニールハウスの老朽化や撤去には、予想以上の出費が発生する場合があります。負担を和らげるためにも、補助金制度をうまく活用すれば、費用負担を大きく減らせるでしょう。
現在、自治体や農業関連団体が行っている補助には次のような種類があります。
- 産地パワーアップ事業(国の農業支援策)
- 自治体独自の農業施設撤去補助金制度
- 再生利用を前提とした環境対策型補助金 など
ただし、産地パワーアップ事業は主に新設・改修支援が目的です。単純な解体撤去への適用は条件が非常に厳しく、多くの場合は対象外となります。
どの制度も共通して「事前申請が必要」であり、解体後の申請は対象外になるため注意が必要です。「もう壊してしまったから今から申請できる?」と考える人もいますが、原則は事前の許可取得が前提です。
また、対象となるハウスの構造(例:鉄骨)や規模、所在地の地域性によって支給の有無が変わります。解体撤去に対する補助制度は地域によって大きく異なり、制度自体が存在しない自治体も多いのが現状です。
そのため、市町村役場の農業振興課やJA窓口で最新情報を確認し、必要書類や申請期限を早めにチェックしておきましょう。補助制度の適用は限定的ですが、条件に合致する場合はコスト削減だけでなく、地域農業の再生にもつながる可能性があります。
まとめ
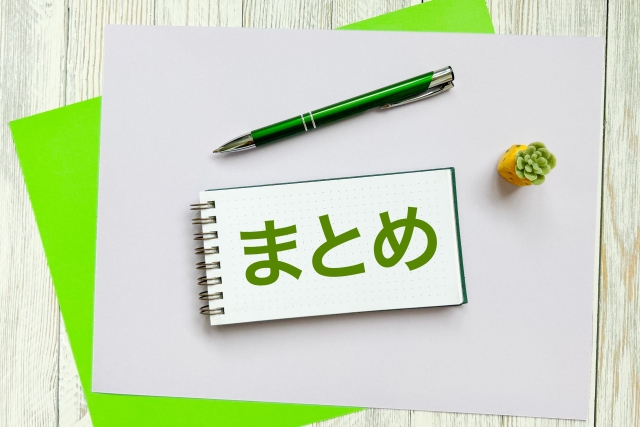
ビニールハウスの解体には、DIYと業者依頼のどちらにもメリット・デメリットがあります。
費用を抑えたい場合は自力解体も可能ですが、構造や規模によっては業者に任せる方が安全で確実です。
また業者に任せる場合の相場は構造別に大きく変動し、追加費用が発生するケースもあります。そのため事前の見積もり確認が必須となってきます。加えて、作業時の注意点や必要な工具も事前に把握しておきましょう。
それに、条件を満たせば補助金が利用できる場合もあるので、自治体やJAへの相談が大切です。
迷った場合は、まずは弊社で簡単にお見積りしてみてください。
こんにちは、解体くん編集部スタッフの山口です。はじめて解体を検討されている方にも安心して読んでいただけるよう、実際の施工事例やちょっとした豆知識を交えて、わかりやすく情報を発信しています。お客様の疑問や不安を少しでも解消できるよう、現場の声をもとにしたリアルな記事づくりを心がけています。もし何か不明点があれば、お問い合わせフォームよりご連絡ください。


