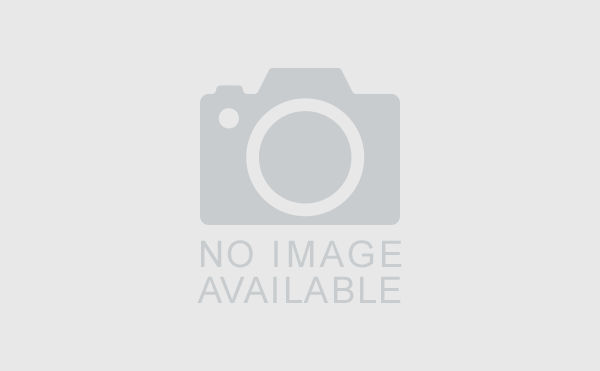解体工事で残置物の撤去は必要?放置のリスクや依頼する費用目安を解説
解体工事を検討する際「家の中にある荷物ってどうしたらいいの?」と悩む方は少なくありません。
家具や家電、日用品など、残された物をそのままにしておくと、工事がスムーズに進まないことがあります。
本記事では、残置物の基本から撤去方法、業者に依頼する費用目安や手順まで解説します。
残置物の撤去を後回しにして後悔しないために、ぜひ最後までご覧ください。
残置物とは?まずは基本の理解から
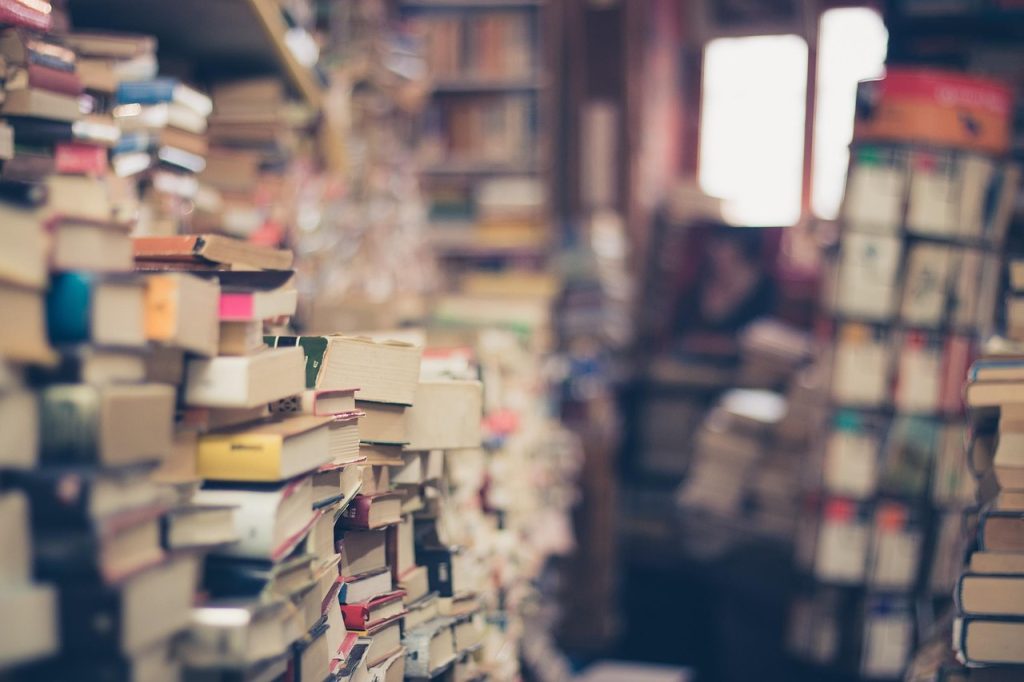
残置物とは、建物の中に置かれたままになっている家具や家電、生活用品などを指します。
たとえば、引っ越し後に置いていかれたソファやタンス、冷蔵庫、食器類などが残置物に該当します。
残置物と似た言葉に「不用品」がありますが、厳密には意味合いが異なります。
不用品は「持ち主が不要と判断した物」であるのに対し、残置物は「所有者が不明なまま残された物」や「まだ必要か判断されていない物」が含まれます。
解体工事の現場では残置物が工事の妨げになるケースがあり、事前の対応が重要です。
なぜ解体工事の前に残置物撤去が必要なの?

解体工事を行なう前に残置物を撤去しておかないと、さまざまなトラブルや追加費用の原因になります。
建物内に物が残ったままだと解体作業の手間が増え、人件費や運搬費がかさみ、見積もりより総合費用が高くなるケースがあります。
また、残置物の撤去を解体業者に丸投げすると、本来の解体工事とは別に処分費用が追加されることもあり、コスト管理が難しくなる可能性にも注意しなければいけません。
安全面でも、可燃物や危険物が混じっていると事故のリスクがあるため、事前の確認と処分が必要です。
無駄な出費やトラブルを防ぐために、残置物の撤去は解体前に済ませておきましょう。
残置物を自分で撤去する方法と費用の目安

残置物は業者に依頼せず、自分で処分することも可能です。主な4つのカテゴリに分けて解説します。
日用品
食器類や衣類、書籍、雑貨などの日用品は、市区町村の可燃ごみ・不燃ごみとして処分できます。
回収日に合わせて少しずつ出せば費用はかかりません。
ただし、量が多すぎると保管スペースや分別作業が負担になるため、必要に応じて自治体の清掃センターへ直接持ち込むのもひとつの手です。
パソコン用品
パソコン本体やプリンターなどのOA機器は、「資源有効利用促進法」により自治体では回収されないことが多いです。
メーカーによる回収サービス(有料または無料)や、宅配で回収してくれるリサイクル業者を利用する方法が一般的で、1台あたり1,000〜3,000円程度が費用の目安となります。
パソコン類を廃棄する際は、内部のデータ消去を忘れずに行ないましょう。
家電
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどは「家電リサイクル法」の対象となっており、リサイクル料金と運搬費用が必要です。
リサイクル券を郵便局で購入し、指定引取場所まで持ち込むか、小売店に引き取りを依頼します。
費用は製品の種類とメーカーによって異なりますが、1台あたり2,000〜5,000円程度を想定しておきましょう。
粗大ごみ
タンスやベッド、テーブルなどの大型家具は粗大ごみに該当し、自治体の粗大ごみ受付センターに申込後、収集日を決めて処分します。
粗大ゴミの処分にかかる手数料は1点あたり300〜1,000円程度が多く、コンビニなどで処理券を購入して貼付するのが一般的です。
大きすぎて運べない場合は、民間の回収業者に依頼するのも手ですが、料金は高めになります。
残置物の処分を業者に依頼する費用目安

残置物の処分を専門業者に依頼する場合、費用は処分する量や内容によって大きく異なります。
たとえば、1Kの部屋なら3万〜5万円前後、2LDKや一戸建ての場合は10万〜30万円程度が相場です。
残置物処分の費用には、仕分け・運搬・処分の作業代や車両代、スタッフの人件費などが含まれます。
また、処分対象に家電リサイクル品や特殊な物品が含まれる場合、追加費用が発生することがあります。
「高いな…」と感じる方もいるかもしれませんが、短時間で大量の荷物を処理できる点では、時間や手間の節約につながるメリットも大きいです。
残置物の処分を業者に依頼する手順

残置物の処分を業者に依頼する場合、スムーズに進めるために手順を把握しておくことが大切です。
①処分物の選定
何を捨てて、何を残すのかをあらかじめ決めておくことで、見積もりや当日の作業がスムーズになります。
写真を撮って記録しておくと、業者とのやり取りが明確になり、トラブルも防げます。
②複数の業者に見積もりを依頼
業者により料金や対応内容が異なるため、必ず複数社から見積もりを取りましょう。
LINEやメールで写真を送るだけで簡易見積もりを出してくれる業者も多く、忙しい方でも手軽に比較できます。
③作業範囲・料金・日程を確認する
見積もりに納得できたら、契約前に「どこまで作業してくれるのか」「追加料金が発生する条件は何か」「作業日はいつか」などを確認しておきましょう。
依頼内容が曖昧なまま進めると、後で予期せぬトラブルになることもあります。
④処分作業の実施
作業当日は立ち会いが基本ですが、遠方の場合などは鍵の預かりや立ち会いなし対応をしてくれる業者もあります。
作業後は、処分内容や部屋の状態を確認し、問題がなければ完了となります。
まとめ

解体工事前に残置物を撤去しておくことは、余計な費用やトラブルを避けるためにとても重要です。
自分で処分する方法もありますが、時間や労力を考えると、業者への依頼が効率的なケースも多くあります。
「とりあえずそのままで…」と先延ばしにしてしまうと、結果的に費用がかさんだり、解体工事が予定通り進まなくなる可能性があります。
早めに行動し、余裕を持って準備を進めて、スムーズな解体工事を行なえる環境を作りましょう!
こんにちは、解体くん編集部スタッフの山口です。はじめて解体を検討されている方にも安心して読んでいただけるよう、実際の施工事例やちょっとした豆知識を交えて、わかりやすく情報を発信しています。お客様の疑問や不安を少しでも解消できるよう、現場の声をもとにしたリアルな記事づくりを心がけています。もし何か不明点があれば、お問い合わせフォームよりご連絡ください。